
福岡で教育イノベーションを - 医療機器メーカーの技術営業から専門学校教員への転身
「1つのことを極めるより、幅広く経験を積みたい」——その言葉が、和田さんのキャリアを象徴しています。
京都大学・大学院を卒業後、医療機器メーカーでの経験を糧に、未知の教育業界へと可能性を広げた和田さん。
家族の未来を見据えた福岡への移住、そして今、最先端のAI×医療教育と向き合う教壇に立つ和田さんの決断には、私たちの働き方や生き方を見つめ直すヒントが詰まっています。
変化を恐れず、自分の価値観に正直に生きる和田さんの転職ストーリーをお届けします。
▼【無料・登録所要時間3分】YOUTURN会員登録はこちらから!
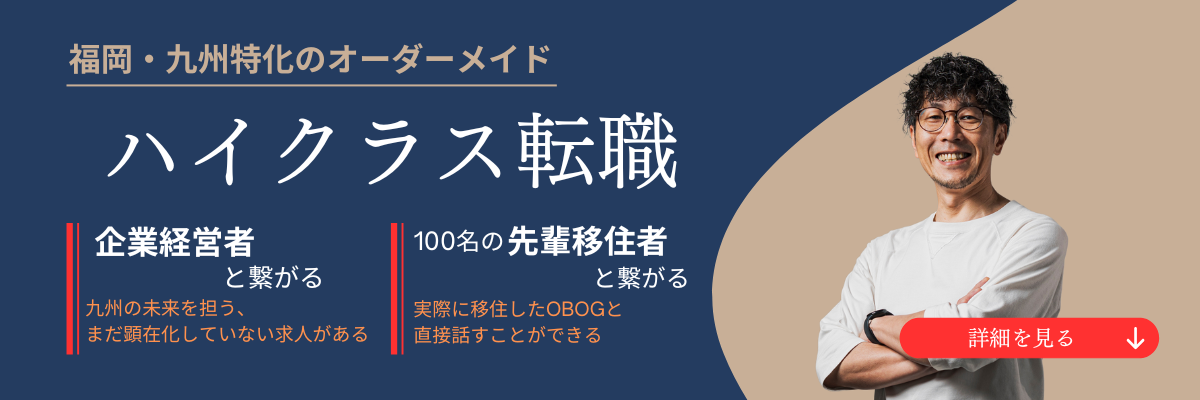
技術と人をつないだ医療機器メーカーでの6年間

——まず、大学・大学院時代について教えてください。
高校の担任の先生が人工血管の開発者だったことがきっかけで、医療機器の開発に興味を持つようになりました。
母が薬剤師ということもあり、医療にはもともと関心がありましたね。大学院の修士課程では、健康診断のデータを活用した病気予測システムの開発研究に取り組んでいました。
特に、肝臓移植のドナーの方が臓器提供の前に行うCT検査をなくすため、血液検査のデータから診断できないかという研究でした。
——就職活動はどのように進めましたか?
実は博士課程に進むつもりだったんですが、知り合いの研究者から「君は博士課程に進学するより企業の研究者になるほうが向いている」と言われて急遽就職活動を始めました。
実際に博士課程に進学する友人たちを見ていると、確かに自分は大学で研究するタイプではないと感じたんです。
1つのことを突き詰めるよりもいろんなことを経験したいという自分の性格を鑑みても、企業に就職したほうがよさそうだと考えたことも理由です。
就職活動は少し出遅れてしまったのですが、幸いにも当時住んでいた関西には医療機器メーカーが多くあったので、大手を中心に選考を受け、内定もいくつかいただきましたね。
——そのなかから1社目の企業を選んだ決め手は何だったのでしょうか。
正直に言えば、人事担当者の雰囲気が一番良かったんです。他社では仕事について淡々と説明されたのですが、同社では仕事の楽しさを伝えてくれました。
また、私は定年まで働くイメージを持っておらず、「5年でどれだけ成長できるか」を重視していました。大企業だと仕事が細分化されますが、同社では一連の業務を経験できると感じたことが決め手になりました。
——入社後はどのような業務を担当されたのでしょうか。
医療業界でいう「学術職」という職種でした。研究開発職と営業職の橋渡し役として、開発部門が作った機械を評価する役割があります。
たとえば「この製品を使って、病気の患者さんのデータでも正確に測定できるか」を病院と連携しながら検証します。
1つの製品に特化するよりも、専門性を持ちつつ、さまざまな製品に触れたかったので、自らこの職種を希望。2年後に営業部門の子会社に転籍となると同時に福岡支社へ転勤。その後、さらに名古屋へ転勤となりました。
子会社への転籍後は技術営業として、営業同行などの外回りを中心に行っていました。お客さまに情報を届けるのが技術営業の仕事だと考えていたので、積極的に外に出ていくようにしていました。
資料作成などの内勤よりも、外出しているほうが好きでしたね。
キャリアと子育ての両立を求めた「福岡」という選択

——順調にキャリアを築いているように感じます。転職を考え始めたきっかけは何だったのでしょうか?
結婚して子どもが欲しいと考えたときに、妻の実家がある福岡か、私の実家がある大阪に戻りたいと思いました。何かあったときに頼れる親族が近くにいる環境が大事だと考えました。
最初は専門知識や経験が活かせる競合他社の福岡支社に応募してみたのですが、仕事上の関係性もあり、なかなか縁がなかったんです。
そのときに「もっと広い視野で考えてもいいかも」と思うようになりました。そこで、YOUTURNに登録しました。
——YOUTURNでは、現在の職場である麻生塾の求人を紹介しました。麻生塾は福岡を中心に九州で専修学校などを運営する総合教育グループです。前職の業界とは異なりますが、どのような印象を受けましたか。
YOUTURNの2回目の面談で紹介された3社のなかに麻生塾がありました。思ってもみなかった業界だったので、「すごいのが来たな」というのが第一印象でした(笑)。
ただ、私は「0から1を作る」より「1を100にする」仕事が得意だと自覚していたこともあり、麻生塾の説明を聞く中で、医療系の新しい学科を立ち上げるというポジション。
「ゼロイチ領域がある程度できているものを、100にする仕事」という印象を受けました。
アイデアを形にしていく仕事は自分のやりたいことと合致していて、新しい分野の先駆者になれるのはおもしろいと感じましたね。
医療機器メーカーで培った医療関連の知見も活かせそうだと感じたのも魅力的に感じた理由です。
———選考プロセスはどのように進んでいきましたか。
カジュアル面談では、「まだ入社するとも決まっていないのにこんなに話をしてくれるんだ」と驚きました。その後はトントン拍子で話が進みました。
ただ、医療系の知識を評価してもらえていると思っていたのですが、面接が進むにつれて「AIやDXの分野で活躍してほしい」と言われて(笑)。
不安がなかったわけではないですが、新しいチャレンジという視点で見ると魅力的なポジションを見出していただいたと思っていますね。
技術と教育の架け橋に。専門学校で見つけた新たな可能性

——入社後はどんな仕事をしていますか。
入社したのは2024年11月で、今は「AI&診療情報管理士科」という新しい学科の立ち上げに携わっています。
入社時は、科目名だけが決まっていて、“箱”だけがあるような状態でした。ここで何を学べるようにするのか、授業の計画を作るところからスタートして、授業の詳細な内容を検討しているところです。
当初は外部講師の方に授業をお願いするのだと思っていたのですが、常勤の社員も担当できるようにしておく必要があるため、自分も授業を行うことになりました。
教鞭を執りはじめたのは入社からわずか1カ月後の12月からなので、準備で大忙しでしたが今は充実しています。
実はYOUTURNコミュニティのメンバーがAIプログラムのサポートをしてくれていて、びっくりしています。
業務委託という形ですが、同じU・Iターン転職を経験してキャリアをどんどん広げていっている姿に刺激を受けています。
——教員として仕事をする中で、新しい気づきはありましたか?
まず私が経験してきた大学生の考え方と、専門学校生ではものの見方がまったく違うことに気づきました。
たとえば自分の出身大学の学生は「いかに効率よく課題をこなすか」を考えがちですが、専門学校の学生はすごく真面目で「言われたことに対して、やるなら完璧にやりたい」という姿勢があります。
非常に新鮮で感心しているところです。
生徒たちの良さを伸ばしつつ、自分がこれまで学んできた学習方法などをハイブリットにして、令和時代の新しい専門学校のスタイルを築いていきたいと思っています。
——新しい分野での学びはいかがですか?
転職してからは本当に学びの連続です。専門学校なので資格試験対策の授業も担当することになり、今は学生が取得を目指す資格を自分も次々と受験しています。
資格マニアのような状態になっていますね(笑)。授業準備として資料作りをしながら勉強することもありますが、特にAI関連の検定や資格は完全に独学です。職場でも学び、家でも学びの毎日ですね。
教員の働き方改革にも挑戦していきたい

——麻生塾での今後の展望をお聞かせください。
今年の秋に子どもが生まれる予定なので、その後も授業を継続できるように、担当授業をすべて動画化して、オンライン授業を画策しているところです。
学生はURLから動画を見て確認テストを受け、私はその成績をネットで確認するという仕組みです。これが成功すれば、ほかの教員にも広げられると思っています。
こうして、普段の業務では教員の働き方改革も意識するようにしています。前職では「残業は効率が悪い」という考えから、定時内で仕事を終わらせることを重視していました。
この働き方を麻生塾でも実践していきたいと考えています。
——最後に、福岡での生活はいかがですか?
福岡はとにかく公私共に「横のつながり」が強く、それが自分にとって居心地の良さにつながっていることを再認識しました。
また子育ての環境としては、やっぱり福岡が一番ですね。妻の実家もあり、サポート体制も整っています。仕事とプライベートのバランスを取りながら、教育業界で新しいことに挑戦し続けたいですね。
編集後記
和田さんの転職ストーリーを取材して、改めて「キャリアとは積み上げるものではなく、広げていくもの」という視点を得ました。
医療機器メーカーでの経験を持ちながら、教育業界で最先端のAI教育に取り組む姿は、キャリアの可能性の広さを示しています。そして、「学び続ける姿勢」の重要性にも気づかされます。
和田さんは新しい環境で、次々と新しい知識を吸収し続けています。
ビジネス環境が大きく変化しつづける現代では、どんな職場でも学び続ける人が強いのだと実感します。
和田さんが教鞭を執る「AI&診療情報管理士科」の学生たちは、先生自身が体現する「学び続ける姿勢」と「異分野への挑戦」から大きな刺激を受けることでしょう。
これからの教育業界に新風を吹き込む和田さんの活躍に、引き続き注目していきたいと思います。




