
<前編>「福岡で経営人材を目指す」移住転職の新しいキャリア戦略
📹 対談のダイジェスト動画を公開中
東京の大企業で安定したキャリアを歩む一方で、「このまま一生この仕事を続けていくのか?」という疑問を抱く20代・30代のビジネスパーソンは少なくありません。
特に、将来的に経営に関わる仕事をしたいと考える人にとって、大企業でそのポジションに到達するまでの道のりは決して平坦ではないはずです。今回は、東京で日本最大手のSler企業でキャリアをスタートし、東京のベンチャーでIPOを経験。
2020年、福岡への移住に伴い、地元スタートアップ・スカイディスクでの営業マネージャーを歴任。その後独立し個人事業主を経て、現在はFCCテクノで新たなチャレンジを始めた伊原さんと、YOUTURN共同代表/高尾が、福岡で経営人材を目指すキャリア戦略について語り合いました。
「地方に来るからには経営人材を目指す」という明確なビジョンを持つ伊原さんの体験談から、従来の「安定志向」とは異なる、新しい時代のキャリア戦略が見えてきます。
<後編はこちらから>
▼【無料・登録所要時間3分】YOUTURN会員登録はこちらから!
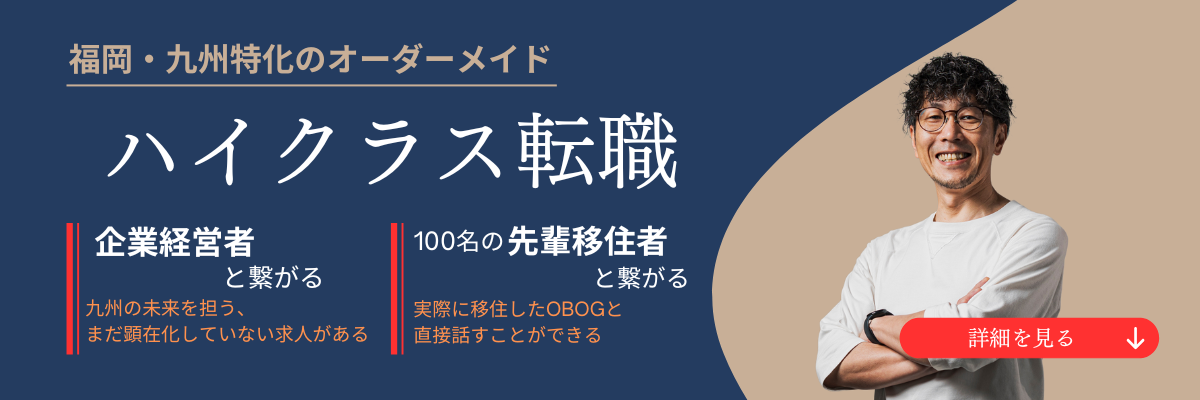
大企業の「仕組み」から飛び出して見えた、地方での経営人材への道筋

――まず、伊原さんが考える「地方での経営人材」というキャリア戦略について教えてください。
伊原さん: 地方に来るからには経営人材、経営に近い仕事をしていくことが重要だと思っています。これじゃないとなかなか年収も上げていけないし、地方の会社はコンパクトなので経営との距離も比較的近いんです。
経営人材として、自分で事業を立ち上げるという方法もあれば、既にある会社の経営陣に上がっていく、あるいは誰かが作った会社を引き継ぐ事業承継もあります。経営人材としてのポジションは結構あるんじゃないでしょうか。
高尾: 移住を考える人たちってウェブで検索すると、営業やオペレーションなどの求人しかないとか、年収半分以下になると思ってしまっている人が多い。でも実際は、違う。YOUTURNから啓蒙していける部分があると思うんです。
伊原さん: 今回FCCテクノでも、経営人材を目指すということで入社させてもらいました。実際に、代表の西村さんや取締役の緒方さんともすごく話しやすく距離が近いと感じます。
――地方だからこそ、経営者との距離が大事になってきますね。
伊原さん: これが東京の大企業で、私が新卒でいた会社で6,000人いるところで事業部長や執行役員と話すとなった時、今38歳ですがこの年齢でも話せてなかったと思います。
同期が400人ぐらいいて、一番優秀な人でも部長ぐらい。経営と密にやり取りするには、大企業だと社会人になって15年ぐらい経っても、よっぽど優秀じゃないとその壁を越えられない。
高尾: 福岡など地方に行った方が経営に近いというのは間違いないですね。
会社規模も違うし、大企業並みの給与を稼ごうと思うと、地方では役職を上げるしかない。マネジメント領域や、エンジニアでもリードエンジニアのポジションに入る必要があります。
「スキル」よりも「マインドセット」〜ベンチャー経験が地方転職で活きる理由

――大企業からベンチャーを経験することで、どのような変化がありましたか?
伊原さん: 大企業にいる時は周りに守られているというか、仕組みがすごいんです。誰がやってもそれなりの会社の規模を維持できているのは、ビジネスモデルや仕組みが半端なくすごいから。でもベンチャーは、そんな仕組みも何もないところで、明日の売上をどう稼ぐか、自分の食い扶持をどう稼ぐかを手探りでやらなきゃいけない。
地方の中小企業も、そんなに仕組みがしっかりある会社は本当に少ない。あったら大企業になってるでしょう。だからこそ、ベンチャーの経験が活きるし、一人でも稼ぐ力、個人事業をやっているような、一人で稼がなきゃいけないマインドが、地方の中小企業に行った時にすごく活きると思います。
高尾: 給料って当たり前に出るもんじゃないんだという経験をするかどうかですよね。
伊原さん: 大企業は仕組みがすごいから、私も新人の頃はすごく鍛えてもらって、いい環境にいたなと今になって思いますが、当時は当たり前だと思っていた。ベンチャーに行くと、そんな環境のない中でやっていかなきゃいけないから、自分がちゃんと強くなって一人で稼げるようにならないとダメだと実感します。
そういう人の方が、地方の会社や九州の会社も喜ぶんじゃないでしょうか。大企業でずっと仕組みの中でやってきた人よりも、ちゃんと一人でも稼ぐ力、そういうマインドセットがある人が、即戦力として欲しいというのはあると思います。
高尾: これはフロントのビジネスサイドの話だけじゃなくて、バックオフィスやコーポレートでも同じことが言えそうですね。
伊原さん: 出来上がったものを運用するのか、自分で全部やるのか、全然違いますよね。1,000人や1万人の経理のシステムと、数百人や数十人の規模の経理は、また違うと思うので、そこに求められるのも変わってくる。そういうスキルがなくても、そういうマインドや考え方がある方が求められると思います。
――スキルとキャリアの関係についてはどう考えていますか?
伊原さん: 私も東京の大企業で、私より営業が上手い人やPMが上手い人は山ほどいましたが、その人が全員福岡に来てめちゃくちゃ活躍できるかというと、環境が違うし、そんなことないでしょう。
スキルとキャリアは別だと思います。スキルだけで出せる影響力には限界があるので、その特定領域の専門性はあるけれども、仕事として成果が出せるか、周りを巻き込んで大きなゴールを達成できるかは、また別の話かなと。
高尾: 地方の生活に馴染めるかどうかも重要ですよね。私たちがYOUTURNコミュニティを運営している理由もそこにあります。
伊原さん: まさに今回FCCテクノへの転職においても、自分自身がちゃんとこの会社に馴染めるかというのは最初のテーマです。「東京から来たんだ!」とか言って踏ん反り返ってる場合じゃなくて、そこの人たちと一緒に巻き込んで結果を出せる方が100倍大事。そこにちゃんと馴染めるかは、不安よりもワクワクしているところです。
「ダークホース」が福岡で輝く〜エリート街道以外のキャリア戦略

――伊原さんがおっしゃっていた「ダークホース」について詳しく教えてください。
伊原さん: 大企業のエリートコースを辿れる人って、結局人数的に限られるんですよね。大企業として評価される人材はいろんなステップがあるし、数値もちゃんと残すとか、上司からも評価しやすいアウトプットを出すとか、いろんな要素がある。
私は多分、上司から評価しやすいアウトプットはあまりなかったんですが、人間的に結構面白い人間だったと思います。そんな人って大企業にいっぱいいて、この組織じゃなくても生きていけるとか、こういうふうにやればもっと伸びる人が実はいるのに、大企業のピラミッドのフィルターだと一握りずつしか上がっていけない。
そのふるいに落ちた人たちは、仕事ではなくプライベートで別の楽しいことをして、自分のパワーやモチベーションを発散していく。それをそのまま仕事に持ってこれるとさらにいいと思うんですが、そういう人たちが私の中ではダークホースです。笑
――地方における経営人材を目指すにあたって、必要なことは何だと考えていますか?
伊原さん: 周りというか、今いる人たちとどううまくやれるかです。「俺は営業で喋れるよ」や「システムでこういうノウハウがあるよ」というよりも、周りを巻き込んで何かできるか、何か問題が来た時にちゃんとその対策や対応を、自分一人で全部やるんじゃなくて、組織でちゃんとやれるかの方が大事だと思います。
大企業は、過去のノウハウやチェックリストがあって、それはノウハウの塊でトラブルが起きないようにしてるんですが、ベンチャーだとそういうのがない。結構出たとこ勝負で、仕組みや組織で助けられないところを、自分が先頭に立ちながらみんなを引っ張っていかなきゃいけない。
そういうのができる人間じゃないと、次の経営人材は難しいと思います。
高尾: 中小企業でも、本当に個人の力量でガッと売り上げを作ってくれる人は頼もしいですが、そういう人は再現性がないし、一人でやってもいいわけです。だったら個人事業や一人社長でやればいい話なので、組織の中でいろんな人がいる中で、きっかけを作ったり、仕組みを作ったり再現性を作ったりする方が喜ばれると思います。
個人事業主から再び組織へ〜「経済圏」を広げるキャリア戦略

――個人事業主を経験された後、なぜ再び組織に入ることを選ばれたのでしょうか?
伊原さん: 高尾さんがよく言っている「自分の周りに経済圏を作る」という言葉がすごくいいなと思っていて、この半年ぐらい、私が持っている経済圏って思っている以上に小さかったなとよく分かりました。
いざスカイディスクをやめてみて、よしこの経済圏でやっていこうと思った時に、意外と小さかった。特に思ったのは、この経済圏の矢印が東京ばかりだということです。
福岡の仕事も1個2個ぐらいあったんですが、大半が東京の仕事や、東京にいた時に仲良くなった取引先やパートナーからで、そこの遺産ばっかりで、経済圏がちっちゃいなと気づきました。
今回FCCテクノに入るきっかけになったのは、経営人材になりたいということもありますが、この経済圏を福岡でもちゃんと大きくしたいと思っていて。
FCCテクノで福岡の会社で働くことによって、新しいパートナーや新しい取引先、福岡で一緒に働く仲間が増えることで、自分が持っている経済圏が東京だけじゃなくて福岡でも広がっていくんじゃないかという期待があって、FCCテクノに入ることにしました。
――会社員になるという発言について、もう少し詳しく聞かせてください。
伊原さん: さっきの馴染むということにかかってて、「俺は経営人材だから」って言って入るのではなく、まずはFCCテクノの一員として、価値を出さなきゃと思ってます。
マインドは常に個人事業主みたいな感じでやってるんですが、まずは自分の意識や周りとしっかり馴染んでから、経営人材を目指す事につながっていければいいと思っています。
変化を楽しむ力〜不確実性の時代に求められるマインドセット
――変化に対する考え方について聞かせてください。
伊原さん: 先のことって分からないなと思ってて、5年前に今のことを想像できたかというと、一個もできていなかった。今もそうですし、あと5年後何をしてるかも分からない。FCCテクノで5年後にどうなっているか分からないし、2、3年してまた個人事業で行きたいと言ってるのか、何をしてるのか分からない。
当然、今の現時点ではFCCテクノで結果を出さなきゃと思ってるんですが、先のことは分からないからこそ、今あるところで仮説検証をひたすらしていくしかない。ただ、多分なんとかなるだろうという変な自信だけはあって、なんとなく大丈夫だろうとずっと思ってるところです。
高尾: 変化対応力がある方とない方がいて、変化対応力がある方は多分どうにかなるだろうと思って変化を起こしに行くから、その起こった変化に対して対応する力が身につくと思うんです。
でも変化対応力が身につかない方は、変化させに行くということに対する躊躇が大きいんだろうなと思っています。
――変化を楽しめるかどうか、福岡に移住された方々はまさに「そちら側の人」です。
伊原さん: そもそも福岡に行くという判断をしている時点で変化するわけです。転職するだけだったら東京でもいいわけで、福岡に行くのは絶対に変化の一歩です。それがワクワクしないんだったら、ちょっとやめた方がいいと思います。
変化する・しないどちらを選んでも、良いことと悪いことが起こる可能性があると思います。だったら変化してマイナスに行った方が、こうしたらマイナスになるんだということが分かる。
でも変化せずにずっと行ってると、後悔先に立たずで、「福岡に行けるチャンスは5年前にあったのに、なんで行かなかったのかな」となる。
どっちにもプラスマイナスがあると思ってるので、だったら変化をする方を楽しめる人がやっぱり福岡に来るべきだと思いますね。
高尾: 確実性の追求を多くの方はしたがる。そっちの方が安心なんですね。でも確実性の追求ほどコストの高いものはない。
伊原さん: 本当にそう思います。今の変化の多い時代に確実性を追求しようとしたら、確実性を追求していたもののベースや、もともとのルールがすぐに変わってしまう。だったら全部それがコストになって無駄になっちゃう。
でも変わるということを前提に、確実性の追求よりも不確実性を許容していく力、その不確実なものを許容しながら前に進んでいく、そういうマインドセットの方がいいのかもしれないです。
<後編はこちらから>





